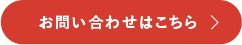デザインに関わること
もう迷わない!伝わる「デザイン依頼書」の書き方ガイド

「思ってたデザインと違う…」そんなズレをなくすカギは、依頼の仕方にあります。
この記事では、誰でもすぐ実践できる“伝わるデザイン依頼書”の書き方を、プロ目線でわかりやすく解説します。
目次
1. デザイン依頼書って何?
2. 依頼書があると何が変わる?
3. 最低限おさえるべき項目
4. 伝わる依頼書にするコツ
5. よくある失敗と回避法
6. すぐ使える依頼書テンプレート
7. プロが「良い依頼書」と感じるポイント
8. デザイン依頼書のDX化
9. まとめ:良い依頼書が良いデザインを生む
1. デザイン依頼書って何?

デザイン依頼書は、「何を・誰に・何のために作るのか」を明文化し、依頼者とデザイナーの認識をそろえる設計書です。ロゴ、チラシ、Web、バナーなど制作物の種類を問わず、品質やスピードを左右します。言葉の解釈違いを防ぎ、修正回数やコミュニケーションコストを下げるのが最大の役割。キーワードは一貫性・再現性・目的適合です。
2. 依頼書があると何が変わる?
依頼書がないと、打ち合わせが増え、指示が感覚的になり、納期や予算がブレがち。一方、デザイン依頼書があると「目的→要件→判断基準」が共有され、初稿の精度が上がって修正量が減ります。結果として納期厳守・コスト最適化・成果最大化が実現。つまり依頼書はプロジェクトの地図であり、迷わないためのガイドです。
3. 最低限おさえるべき項目
依頼内容(ロゴ/チラシ/Webなど)、目的(集客・認知・採用など)、ターゲット(年齢・職業・課題)、参考デザイン(URLや画像)、納期(初稿と最終の2段階)、納品形式(ai/png/pdf/Figma)、予算レンジ、制作範囲(デザインのみ/原稿・撮影の有無)、ブランドトーン(信頼感・親しみ・高級感)、使用シーン(SNS広告・展示会パネル・LPヒーロー画像)。まずはここを網羅しましょう。
4. 伝わる依頼書にするコツ

①目的を先に書く:「展示会来場を増やす」「採用エントリー率を上げる」など。②感覚語を具体化:「おしゃれ」→「20代女性がSNSでシェアしたくなる明るいトーン」。③譲れない点と任せる点を分ける:ロゴの使用ルールは固定/色味は提案歓迎。④使用シーンを添える:どこで・どれくらいの期間・どのデバイスで使うか。これだけでデザイン依頼書の解像度が上がります。
5. よくある失敗と回避法
「急ぎで!」だけでは手戻りが増えます→中間チェック日を設定。「明るくして」など抽象的な修正→色番号・フォント名・余白量を数値で指定。関係者が多く意見が割れる→社内窓口を一人に統一。法的・ブランド制約の抜け漏れ→禁止事項・商標表記ルールを依頼書に明記。デザイン依頼書に判断基準を埋め込むのがコツです。
6. すぐ使える依頼書テンプレート
【デザイン依頼書】案件名/目的(達成したい指標)/ターゲット(年齢・職業・行動)/制作物の種類(ロゴ・バナー・LP等)/使用媒体(Web・印刷・SNS)/希望デザイン(色・トーン・参考URL・競合例)/サイズ・仕様(pxまたはmm)/納期(初稿日・最終納品日)/納品形式(ai・png・pdf・Figma等)/使用素材(ロゴ・写真・テキスト)/禁止事項・法的留意点/運用方法(掲載期間・媒体)/その他特記事項。社内標準フォーム化すると毎回の負担が激減します。
7. プロが「良い依頼書」と感じるポイント

最初に目的とターゲットが明快、使用シーンと運用期間がセット、判断基準(可否の軸)が書かれている、そしてクリエイティブ裁量の余白が残っていること。完成を「納品で終わり」でなく「使って成果を出す」と定義しているデザイン依頼書は、提案の質が上がり、費用対効果も高まります。
8. デザイン依頼書のDX化
GoogleフォームやNotionでオンライン化し、必須項目を設計すると抜け漏れが激減。フォーム回答をプロジェクト管理(Asana/ClickUp等)に自動連携すれば、初稿日やレビュー日も可視化できます。初期ヒアリングをAIで要約し「デザイン依頼書のたたき」を自動生成するワークフローを用意すると、スピードと正確性が両立します。
9. まとめ:良い依頼書が良いデザインを生む
デザイン依頼書はチェックリストではなく、チームの共通言語です。目的と言葉を具体化し、使用シーンまで共有できれば、修正は減り、納期は守られ、成果は最大化。デザインは「お願いする」ものではなく「一緒につくる」もの。その第一歩は、精度の高いデザイン依頼書から始まります。
【広報宣隊】では定額制で、SNS広告はもちろん、チラシやポスター、動画作成など、様々なデザインを通してブランディングとデザインの力を最大限に活用し、販促活動の成功をサポートします!
デザインについてお困りの方や、どの企業に依頼するかご検討している方がいらっしゃいましたらお気軽にご連絡ください。
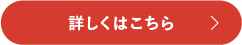
また、広報宣隊のサブスクリプションに興味、相談がある方は、まずはお気軽に広報宣隊のお問い合わせフォームからお気楽にご相談ください!