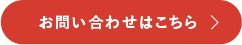デザインに関わること
初心者でもわかる!「デザイン用語集」

「打ち合わせで“トーン&マナー”とか“UX”って言われても、正直ピンとこない…」
そんなあなたのために、デザインの現場でよく使われる言葉を、やさしく・わかりやすくまとめました。
この記事を読めば、今日からデザイナーとの会話がスムーズになります!
目次
1. デザインの基本用語
2. レイアウトと構成の用語
3. 配色とフォントの用語
4. UI・UXの用語
5. デザイン用語を実務で活かすコツ
6. まとめ:用語を理解すれば、デザインはもっと伝わる
1. デザインの基本用語

デザインとは「見た目を整えること」ではなく、目的を達成するための設計のことです。 「誰に・何を・どう伝えるか」を明確にし、それをビジュアルで表現するのがデザインの役割です。
その中心にあるのがコンセプト。 コンセプトとは、デザイン全体を貫く考え方や軸のことで、目的・ターゲット・伝えたい価値を一言で表します。 コンセプトがあることで、色・形・写真・フォントなどが統一され、見る人に自然と伝わるデザインになります。
たとえば「安心感を与えるデザイン」にしたいなら、柔らかい色合いと丸みのある形を選び、全体のトーンを揃えることが大切です。
2. レイアウトと構成の用語
レイアウト(配置)はデザインの基本です。情報をどう配置するかで、見やすさも印象も大きく変わります。
- グリッドレイアウト: 見えない線を基準に要素を整列させる設計手法。新聞やWebサイトで多用されます。
- ヒエラルキー: 情報の優先順位を整理し、タイトル → 見出し → 本文の順に視線の流れを作ること。
- 余白(ホワイトスペース): 情報を引き立てる「間」のこと。詰め込みすぎず、余裕のあるレイアウトが読みやすさと信頼感を高めます。
レイアウト設計で最も重要なのは、「どこを見ればいいか」がすぐ分かること。 視線誘導のあるデザインは伝わりやすく、印象にも残ります。
3. 配色とフォントの用語
色と文字は、デザインの印象を決定づける要素です。
- トーン&マナー: ブランド全体の雰囲気を統一する考え方。広告・Web・SNSなどすべての媒体で一貫性を持たせます。
- コントラスト: 明るさや色の差。背景と文字のコントラストが弱いと読みにくくなるため、十分な差を確保することが重要です。
- 補色: 色相環で反対側にある色。青とオレンジなど、印象を強めたいときに効果的です。
- セリフ体/サンセリフ体: フォントの種類。セリフ体(明朝体)は信頼感・上品さ、サンセリフ体(ゴシック体)はシンプルで現代的な印象を与えます。
補足: 社内資料で「読みづらい」と感じたときは、まずフォントサイズとコントラストを見直すのが基本です。
4. UI・UXの用語
デジタルデザインに欠かせないのが、UI(ユーザーインターフェース)とUX(ユーザーエクスペリエンス)です。
- UI: ボタンやメニューなど、ユーザーが実際に触れる操作部分の見た目や構成。
- UX: ユーザーがサービスを通じて得る体験全体。使いやすさや心地よさをデザインで支えること。
UIは「触れる部分」、UXは「感じる部分」。 この2つをバランスよく設計できるかどうかが、デジタル時代のデザインの質を左右します。
また、アクセシビリティ(誰でも使える設計)や レスポンシブデザイン(端末に応じた最適化)もUX向上には欠かせません。
5. デザイン用語を実務で活かすコツ
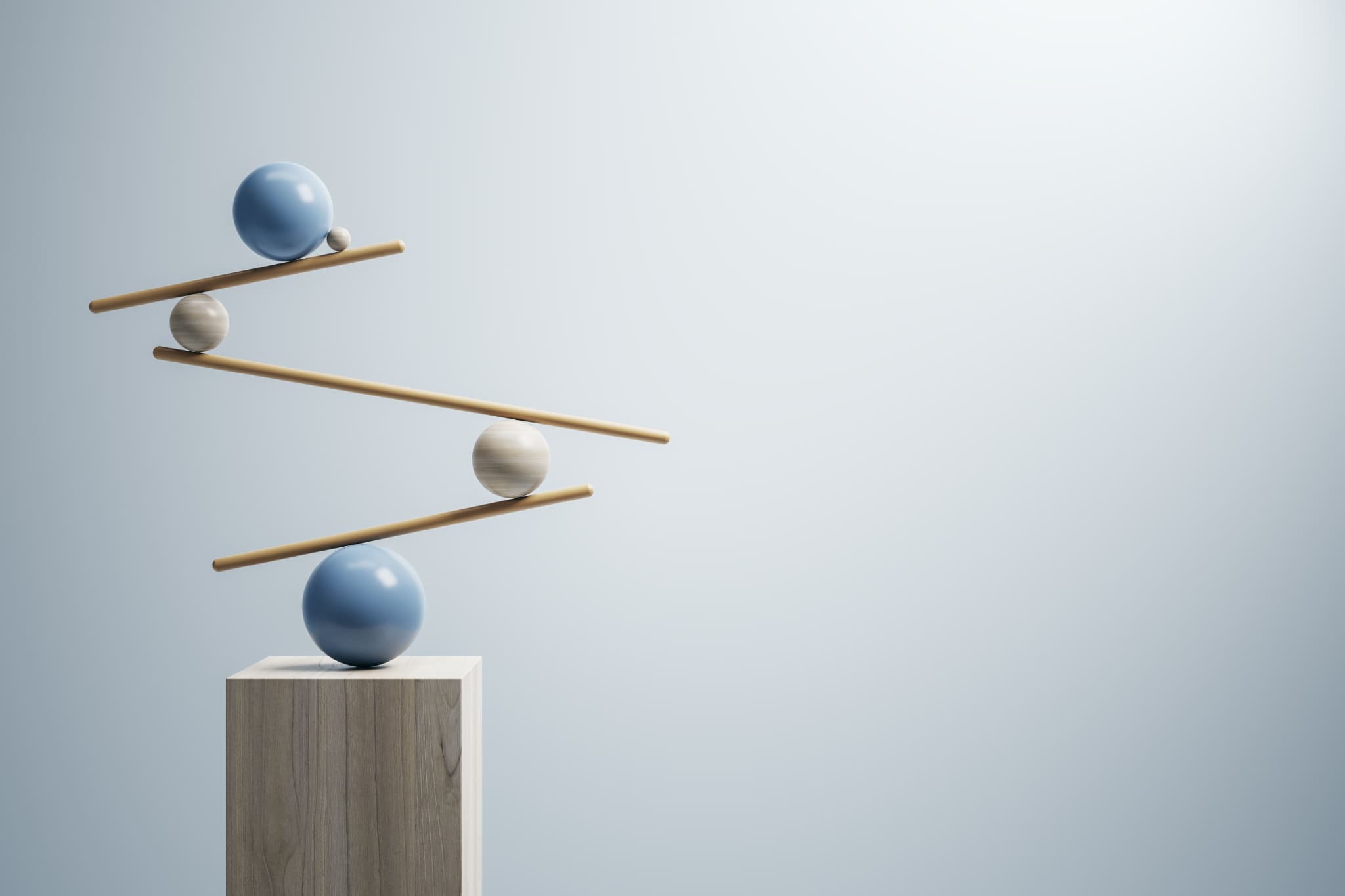
用語は「知っている」だけでなく、「使いこなす」ことが大切です。以下の3つを意識しましょう。
- 相手に合わせて言葉を選ぶ: 専門用語ばかりを並べず、相手が理解できる表現に言い換える。
- 感覚ではなく用語で伝える: 「なんか違う」ではなく、「余白を広げたい」「コントラストを上げたい」と具体的に伝える。
- 目的で分類する: 「見やすくする用語」「印象を決める用語」「行動を促す用語」など、目的別に整理して覚える。
補足: 社内の打ち合わせでは、用語を共通言語にすることで認識のズレが減り、修正や承認がスムーズになります。
6. まとめ:用語を理解すれば、デザインはもっと伝わる
デザイン用語は、専門家だけのものではありません。 正しく理解すれば、デザイナーと同じ目線で会話ができ、成果につながるコミュニケーションが可能になります。
そして、言葉を“感覚”から“共通理解”に変えることで、デザインの価値はさらに高まります。 今日からぜひ、この用語集を現場で活用してみてください。
【広報宣隊】では定額制で、SNS広告はもちろん、チラシやポスター、動画作成など、様々なデザインを通してブランディングとデザインの力を最大限に活用し、販促活動の成功をサポートします!
デザインについてお困りの方や、どの企業に依頼するかご検討している方がいらっしゃいましたらお気軽にご連絡ください。
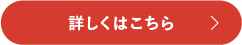
また、広報宣隊のサブスクリプションに興味、相談がある方は、まずはお気軽に広報宣隊のお問い合わせフォームからお気楽にご相談ください!